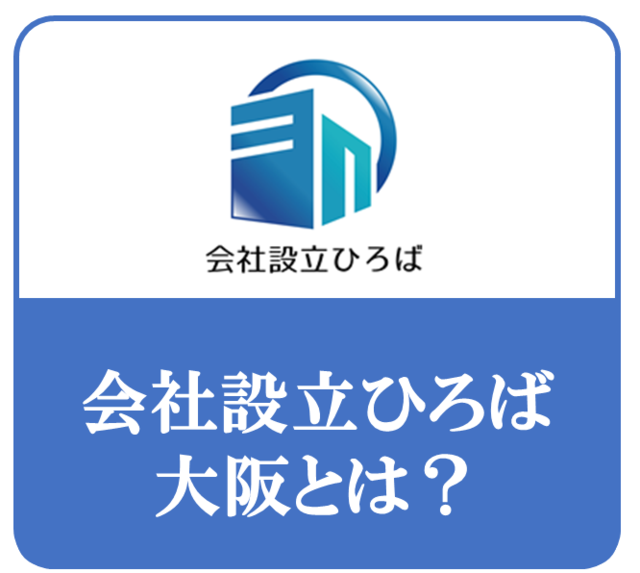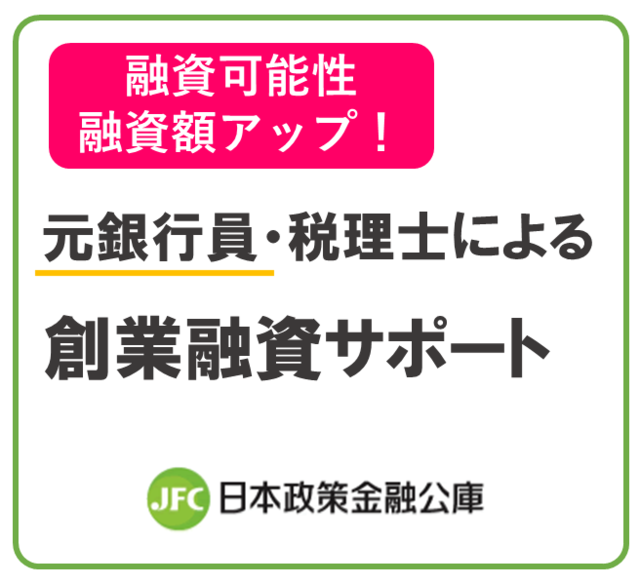大阪で会社設立・創業融資・起業・開業支援なら、当事務所にご相談ください。【大阪のほか京都・神戸など近畿全域に対応】。

大阪で会社設立・創業融資のことなら「会社設立ひろば 大阪」
大阪府大阪市北区堂島2丁目1−27 桜橋千代田ビル2階
受付時間:9:00〜18:00、定休日:日曜日・祝日(電話対応可能)
無料相談実施中
お気軽にお問合せください
お気軽にお問合せください
06-6147-7990
定款の認証手続き

作成した定款は、公証役場で”認証”という手続きを受けることが必要となります。”認証”とは、発起人が作成した定款に間違いがないかを、公証人という人が確認して証明することです。会社を作るときだけこの定款の認証が必要となります。
ここでは、定款の認証の際に必要な書類や手続きについて説明しています。
紙定款の認証の際に必要な書類
定款が完成したら、次は公証人による認証を受けます。認証を行うことができる公証人は、本店所在地の都道府県を管轄する法務局に所属する公証人です。本店所在地がある都道府県内になる公証役場で認証すると考えておけばよいでしょう。例えば、大阪府に本店所在地がある場合は、大阪市内でも高槻でも枚方でも大阪府内の公証役場であればOKです。
公証役場へは訪問して認証を受ける必要がありますが、訪問の前に、定款の記載内容に誤字脱字がないか、絶対的記載事項に漏れがないかを、事前にチェックしてもらうため、所轄の公証役場に定款をFAXもしくは電子メールで送ります。その後、内容のチェックが終われば、公証役場への訪問日時を予約することになります。
定款の認証を受けに公証役場に行くときに必ず持っていくもの
- 押印済みの定款:3通
- 発起人全員の印鑑証明書:各1通
- 発起人全員の実印:定款に捨印を押印することで不要になります
- 運転免許証など顔写真入りの本人確認資料
- 収入印紙:4万円(電子認証の場合には不要となります)
- 公証人の手数料と定款の謄本の交付手数料:約5万2千円
ご自分で定款の認証を行うことを前提とした必要書類になります。
定款認証日には、原則として発起人全員が公証役場へ行く必要があります。しかし、発起人で公証役場に立ち会えない人がいる場合には、代理人を立てることができます(第三者でもOKです)。その場合には、委任状を作成して個人の実印を押印し、公証役場に提出すれば大丈夫です。
訂正があった場合に備えて、あらかじめ定款に捨印を押しておくことが一般的です。そうすることで、当日発起人の実印を持っていく必要がなくなります。
認証に立ち会うか否かに関係なく、発起人全員の個人の印鑑証明書は必要です。発起人が会社(法人)である場合には、その会社の登記事項証明書と印鑑証明書を持っていきます。
収入印紙は事前に購入して、定款3通のうち、1通に4万円の収入印紙を添付しておきます。収入印紙が貼ってあるものは、定款の原本として公証役場に保管されます。収入印紙を貼っていない残りの2通のうち、1通は法務局に提出する定款の謄本として使用し、残り1通は原始定款として会社に保存しておきます。ただし、定款の電子認証を行う場合には4万円の収入印紙は不要となります。
その他負担する費用として、公証人の認証手数料として5万円を公証役場訪問時にその場で支払います。このほか、定款の謄本交付手数料として、謄本1通につき250円の費用がかかります。
定款の認証を受けに公証役場へ行くとき、場合によって持っていくもの
- 委任状:公証役場へ行くことができな発起人がいるとき
- 代理人の印鑑証明書:発起人以外が代理人の場合
- 登記事項証明書:会社が発起人の場合
電子定款の認証の際に必要な書類
電子定款の場合も、紙の定款と同じように公証役場へ出向く必要があります。電子メールで認証が行えるというようなことはありません。異なる点としては、発起人側で定款を印刷して、印紙を貼ったり、押印したりすることが不要なことです。
認証を受けるまでの流れ(事前に電子メールなどでチェックを受けるなど)は紙の定款と変わりません。事前チェック後、公証役場に行く日時を予約しますが、その際、電子定款を保存するCD-RやUSBメモリのどちらを用意するかも確認するようにしましょう。
電子定款の認証を受けに公証役場に行くときに必ず持っていくもの
- 委任状:公証役場へ行くことができない発起人がいるとき
- 発起人全員の印鑑証明書:各1通
- 運転免許証など顔写真入りの本人確認資料
- 公証人の手数料と定款の謄本の交付手数料:約5万2千円
- 電子定款保存用CD-RまらはUSBメモリ
電子定款の場合も、公証人による認証が必要になります。公証役場へ定款を送信後※、公証役場に出向きます。
※電子定款の作成には”電子署名”をした定款のPDFファイルを、所定のオンライン申請用ソフトを使用して事前に公証役場に送信しておく必要があります。手間やソフトウェアの容易にかかる費用を考えると、専門家に依頼することがベターな選択とは思います。
発起人が複数人いる場合には、電子署名をした発起人が代表して公証役場へ行きます。電子定款はシステム上、発起人の代表者が送信するため、公証役場へ行くのは、発起人の代表者のみでかまいません。
他の発起人は委任状を作成し、電子署名をした発起人に渡します。電子定款の場合の委任状は紙の定款とは記載内容が異なるため注意が必要です。
会社設立・起業・創業融資・資金調達の無料相談はこちら

大阪、京都、神戸の株式会社設立・合同会社設立・一般社団法人設立・個人開業、創業融資のご相談は会社設立ひろばまで!
お電話でのお問合せはこちら
06-6147-7990
受付時間:9:00〜18:00
定休日:365日メールでのご相談は対応いたします。
※電話は転送されますので、日曜日・祝日であっても、お電話は承ります。つながらない場合は、ご面倒ですがメールにてお問合せいただけると幸いです。
メールでのお問い合わせは下記のメールお問合せフォームにてお問合せください。